| 年代 | 出来事 | 人物 | 語呂合わせ |
|---|---|---|---|
| 1665年 | 細胞の発見 | ロバート・フック | 色むごい(1665)細胞、フックが名付ける |
| 1671年 | 水素の発見 | ロバート・ボイル | ヒーローない(1671)ボイル、水素を発見 |
| 1772年 | 窒素と酸素の発見 | ルザフォ(窒素)、シェーレ(酸素) 、イングェンハウス | いーな、なに(1772)ルザフォ窒素、シェーレ酸素、イングェンハウス光合成 |
| 1789年 | 炭素の発見 | ラヴォワジエ | いいな役(1789)、ラヴォワジエが炭素を発見 |
| 1806年 | アミノ酸の発見 | ヴォーケラン、ロビケ | いーわ、おむすび(1806)、ヴォーケランとロビケがアミノ酸発見 |
| 1828年 | 尿素の合成 | フリードリヒ・ヴォーレル | いや、ニッパ(1828)、ヴォーレルが尿素を合成 |
| 1868年 | 核酸の発見 | フリードリヒ・ミーシャー | 人はロバ(1868)、ミーシャーが核酸発見 |
| 1878年 | クロマチンの発見 | ウォルター・フレミング | 人は悩み(1878)、フレミングがクロマチン発見 |
| 1885年 | 酵素の用語導入 | ヴィルヘルム・キューネ | いいやご飯(1885)、キューネが酵素の名付け親 |
| 1903年 | 生化学の用語導入 | カール・ネウベルグ | 行くぜお散歩(1903)、ネウベルグが生化学を導入 |
| 1929年 | ATPの発見 | カール・ローマン | 行く肉(1929)、ローマンがATPを発見 |
| 1937年 | TCAサイクルの発見 | ハンス・クレブス | いくみんな(1937)、クレブスがTCAサイクル発見 |
| 1940年 | 解糖系の経路解明 | グスタフ・エムデン、オットー・マイヤーホフ、ヤコブ・パルナス | ひどく良い(1940)エムデンらが解糖系解明 |
| 1947年 | コリ回路の発見 | フェルディナンド・コリ、ゲルティ・コリ | ひとくしな(1947)、コリ夫妻がコリ回路発見 |
| 1950年 | チャーガフのルール | エルヴィン・チャーガフ | 行くゴミ(1950)チャーガフ、ルールを発見 |
| 1952年 | ミラー・ウレーの実験生命の起源 | スタンリー・ミラー、ハロルド・ウレー | 行く後に(1952)、ミラーとウレーが実験成功 |
| 1953年 | 二重螺旋モデルの発表 | ジェームズ・ワトソン、フランシス・クリック | 行くゴミさん(1953)、ワトソンとクリックが二重螺旋 |
| 1961年 | 遺伝コードの解明 | マーチン・ニーレンバーグ、ハインリッヒ・J・マッタイ | 行く無意味(1961)なし、ニーレンバーグらが遺伝コード解明 |
| 1970年 | 中央教義の確立 | フランシス・クリック | 行くなれ(1970)、クリックが中央教義確立 |
| 2000年以降 | ゲノム時代の到来 | ゲノムプロジェクト | 未来(2000)へ進む、ゲノムプロジェクト |
1665年 – 細胞の発見
ロバート・フック(Robert Hooke)
イギリスの科学者ロバート・フックが顕微鏡を用いて細胞を初めて観察し、その構造を「細胞」と名付けました。彼はコルクのスライスから細胞壁の構造を観察しました。
1671年 – 水素の発見
ロバート・ボイル(Robert Boyle)
ボイルは、水素の存在を示す実験を行い、水素が化学反応に関与することを発見しました。
1772年 – 窒素と酸素の発見
ダニエル・ルザフォ(Daniel Rutherford)
窒素を発見し、空気中の酸素とともに化学的性質を研究しました。
カール・ウィルヘルム・シェーレ(Carl Wilhelm Scheele)
酸素を発見し、酸素の役割について詳細な研究を行いました。
ヤン・イングェンハウス(Jan Ingenhousz)
光合成の過程を発見し、植物が光の下で酸素を放出することを示しました。
1789年 – 炭素の発見
アントワネット・ラヴォワジエ(Antoine Lavoisier)
炭素を発見し、化学の基礎を築く上で重要な役割を果たしました。
1806年 – アミノ酸の発見
ルイ=ニコラ・ヴォーケラン(Louis-Nicolas Vauquelin)とピエール=ジャン・ロビケ(Pierre Jean Robiquet)
アスパラギンというアミノ酸をアスパラガスから抽出しました。
1828年 – 尿素の合成
フリードリヒ・ヴォーレル(Friedrich Wöhler)
無機物質から尿素を合成し、有機化学が無機化学から独立した分野であることを証明しました。
1868年 – 核酸の発見
フリードリヒ・ミーシャー(Friedrich Miescher)
白血球から「ヌクレイン」と呼ばれる物質を発見し、後にこれが核酸(DNA)であることが分かりました。
1878年 – クロマチンの発見
ウォルター・フレミング(Walter Flemming)
クロマチンの存在を発見し、細胞分裂の過程における役割を示しました。細胞遺伝学の父と呼ばれています。
1885年 – 酵素という用語の導入
ヴィルヘルム・キューネ(Wilhelm Kühne)
「酵素」という用語を初めて使用し、酵素の概念を紹介しました。
1903年 – 生化学という用語の導入
カール・ネウベルグ(Carl Neuberg)
「生化学」という用語を導入し、生物学と化学の統合的な分野を定義しました。
1929年 – ATPの発見
カール・ローマン(Karl Lohmann)
ATP(アデノシン三リン酸)を発見し、エネルギーの代謝に関する重要な情報を提供しました。
1937年 – TCAサイクルの発見
ハンス・クレブス(Hans Krebs)
TCAサイクル(クエン酸回路)を発見し、細胞のエネルギー生産のプロセスを明らかにしました。
1940年 – 解糖系の経路の解明
グスタフ・エムデン(Gustav Embden)、オットー・マイヤーホフ(Otto Meyerhof)、ヤコブ・カロル・パルナス(Jakob Karol Parnas)
解糖系(グリコリシス)の経路を解明し、細胞内でのエネルギー生成の理解を深めました。
1947年 – コリ回路の発見
フェルディナンド・コリ(Ferdinand Cori)とゲルティ・コリ(Gerty Cori)
コリ回路(グリコーゲンの代謝経路)を発見し、糖の代謝に関する重要な洞察を提供しました。
1950年 – チャーガフのルール
エルヴィン・チャーガフ(Erwin Chargaff)
DNAの塩基対の比率に関する「チャーガフのルール」を発見し、遺伝子の構造と機能に関する理解を深めました。
1952年 – ミラー・ウレーの実験
スタンリー・ミラー(Stanley Miller)とハロルド・ウレー(Harold Urey)
生命の起源に関する実験(ミラー・ウレー実験)を行い、原始地球の条件下で有機分子が形成される可能性を示しました。
1953年 – 二重螺旋モデルの発表
ジェームズ・ワトソン(James Watson)とフランシス・クリック(Francis Crick)
DNAの二重螺旋構造を提案し、遺伝子の情報伝達のメカニズムを解明しました。
1961年 – 遺伝コードの解明
マーチン・ニーレンバーグ(Marshall Nirenberg)とハインリッヒ・J・マッタイ(Heinrich J. Matthaei)
遺伝コードを解読し、RNAからタンパク質への翻訳のメカニズムを明らかにしました。
1970年 – 分子生物学の中心的な教義
フランシス・クリック(Francis Crick)
分子生物学の中心的な教義(中央教義)を確立し、遺伝子の情報がDNAからRNAを経てタンパク質に転送される過程を説明しました。
2000年以降 – ゲノム時代とポストゲノム時代
ゲノムプロジェクトの成果
ヒトゲノムプロジェクトの完成とそれに続く研究により、ゲノムの全体像が明らかにされ、個別化医療やゲノム編集技術などの新しい展開が始まりました。

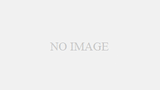
コメント