Contents
- 1 目的
- 2 他人の評価について
- 3 誰が倫理を決定するのか?
- 4 ステップ1: 事実の把握と検討
- 5 ステップ2: 価値の特定
- 6 ステップ3: 最も難しいケースの反映
- 7 ステップ4: 一貫性の確認
- 8 コンフリクトヘルプライン: 手助けするか否か
- 9 賢明な決定に達する
- 10 原則 (Principle)
- 11 バイオメディカル倫理の原則
- 12 自律性 (AUTONOMY)
- 13 自発性 (VOLUNTARINESS)
- 14 強制 (COERCION)
- 15 説得 (PERSUASION)
- 16 操作 (MANIPULATION)
- 17 能力 (COMPETENCY)
- 18 父権主義 (PATERNALISM)
- 19 1. 自律性の尊重(Respect for Autonomy)
- 20 2. 善行(Beneficence)
- 21 3. 無危害(Non-maleficence)
- 22 4. 正義(Justice)
目的
- 人間科学と哲学、そしてその多様性を理解する
- 医療におけるバイオメディカル倫理の核心原則を適用する
- 倫理的意思決定の要素に慣れる
他人の評価について
- 全員を満足させることはできない
- 何をしても批判する人はいる
- だから、自分が正しいと信じることをして、批判に惑わされないことが重要
- 人々は、何が正しいか、何が間違っているかについて意見が異なることが多い。たとえ一致した意見があっても、その理由は異なることがある
誰が倫理を決定するのか?
- 社会によって異なる
- リベラルと伝統的な考え方
- 文化や宗教
- 政治的影響
- 社会的圧力
- グローバルレベルでは、WMA(世界医師会)が医師に要求される行動を広範に示す倫理的声明を設定している
- 医療協会の倫理指針は一般的な性質を持ち、医師が直面するすべての状況に対応できるわけではない
- 多くの状況で、医師は自分でどのように行動するかを決定しなければならないが、他の医師が似た状況でどのように行動したかを知ることは役立つ
- 医療実践において、医療協会からの指針がない倫理的問題が多く存在する
- 最終的には、個人が自分の倫理的決定を下し、それを実行する責任がある
- 医療バイオエシックスは、健康専門職が混乱や対立に直面したときに参照できる有益な価値観に基づいている
- 重要な目標は、正しい決定を下すこと
ステップ1: 事実の把握と検討
- 事実の慎重な分析: 状況を理解するために、医療事実を慎重に分析することが重要です。
- 検討に影響を与える要素:
- 教育: 知識と学習の程度が意思決定に影響します。
- 文化的背景: 出身文化や習慣が判断に影響します。
- 個人的な専門知識: 専門知識や技術が意思決定に影響を与えます。
- 経験: 過去の経験が意思決定に反映されます。
ステップ2: 価値の特定
- 問題となる価値の特定: 問題として提示される価値がどれかを特定することが重要です。
- 価値の対立:
- 尊重?正義?などの異なる価値が衝突する場合があります。
ステップ3: 最も難しいケースの反映
- 意思決定における課題: 決定の際に生じる課題を検討します。
- 代替行動が他の価値を尊重しない可能性:
- 例: エホバの証人が必要な輸血を拒否するが、医師には命を救うことを求める場合
- 最良の結果: 最も良い結果が最も良い選択であると考えられます。
ステップ4: 一貫性の確認
- 検討と反映の一貫性: 正しい決定を目指す倫理的目標に沿って一貫していることを確認します。
- 道徳的基準、行動、価値観の整合性: 矛盾しないようにすることが重要です。
- 一貫して道徳的か、一貫して非道徳的か: 偏見を持った判断は避けるべきです。
コンフリクトヘルプライン: 手助けするか否か
- 法律の参照:
- 法律は倫理的な問題を解決できないかもしれませんが、市民の道徳的価値観を反映しています。不正や不満足な結果が生じることもあります。
- 公開テスト:
- 自分の行動が公に知られたとしても同じように振る舞うかどうかを考えるテストです。
賢明な決定に達する
- 適切な戦略の選択: 問題を探求するための適切な戦略を選びます。
- 実践的な知恵:
- 良く考えられた決定を行う芸術であり、道徳的な美徳の最たるものです。
- よく考えられた決定:
- 必ずしも普遍的に合意されるものではないかもしれませんが、深く考慮された決定です。
以下は、バイオメディカル倫理に関する主要な概念と原則についての日本語での解説です。
原則 (Principle)
- 規則 (RULE)
- 規範 (PRECEPT)
- 標準 (STANDARD)
- 形式 (FORM)
これらは、行動を導くための最も一般的で包括的な規範を提供します。
バイオメディカル倫理の原則
- 原則主義的な方向性を持つとされるアプローチ
- プリンシプルズム (Principlism) として知られる方法論
- バイオメディカル倫理の4つの原則アプローチ
- ジョージタウン・マントラ(Georgetown Mantra)と呼ばれます。
自律性 (AUTONOMY)
- 独立 (INDEPENDENCE)
- 自由 (FREEDOM)
- 解放 (LIBERTY)
- 自己決定 (SELF-DETERMINATION)
- **”Autos”(自己) “nomos”(規則)**から由来します。
- 最も基本的な人権です。
- 個人が自由に個人的な問題について情報を基に決定できる能力を尊重する社会に根ざしています。
- 自由を奪わないことが重要です。
- 患者の選択が自律的な選択と見なされるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 患者が自発的に選択すること。
- 選択が十分に情報提供されたものであること。
- 患者が意思決定能力を持っていること。
自発性 (VOLUNTARINESS)
- 故意 (DELIBERATE)
- 意識的 (CONSCIOUS)
- 意図的 (INTENDED)
- 自発的 (WITTING)
- 「人が他者の影響下にない状態で行動を意図する程度において、その行動を自発的に行う」と定義されます。
強制 (COERCION)
- 強要 (COMPULSION)
- 制約 (CONSTRAINT)
- 力 (FORCE)
- 「ある人物が他者をコントロールするために、信頼性があり重大な危害の脅威や力を意図的に使用する場合」に発生します。
- これにより、意図的で十分に情報提供された行動であっても、自律的ではなくなります。
説得 (PERSUASION)
- 誘導 (INDUCEMENT)
- 勧告 (EXHORTATION)
- 「他者が提示する理由のメリットを通じて、人が何かを信じるようになるプロセス」を指します。
操作 (MANIPULATION)
- 操縦 (MANEUVER)
- 争う (CONTEND)
- 誘導 (NADE)
- 「説得でも強制でもない影響の形態」を指します。
- 操作の本質は、強制や説得以外の手段で、人を操作者が望む方向に動かすことです。
能力 (COMPETENCY)
- 能力 (CAPACITY)
- 適性 (APTITUDE)
- キャパシティ (CAPABILITY)
- 特定の決定を行うための能力を指します。
- バイロン・チェル (Byron Chell) は一般に「人が状況と決定の結果を理解し、その決定が合理的な理由に基づいている場合、その人は有能と見なされる」と述べています。
父権主義 (PATERNALISM)
- 権威 (AUTHORITY)
- 父親 (FATHER)
- コントロール (CONTROL)
- 「ある人の既知の好みを、別の人が意図的に覆すことで、好みが覆された人の利益や害を避けるために行動が正当化される場合」を指します。
バイオメディカル倫理の4つの原則アプローチ(The Four Principles of Biomedical Ethics)とは、医療倫理において広く認められている4つの基本的な倫理原則を基に、医療従事者が倫理的な意思決定を行うための枠組みです。これらの原則は、**「ジョージタウン・マントラ(Georgetown Mantra)」**とも呼ばれ、患者ケアの様々な状況に適用されます。以下に、その4つの原則を説明します。
1. 自律性の尊重(Respect for Autonomy)
- 自律性とは、個人が自分の人生に関する決定を自ら行う権利を持つことを意味します。
- 患者の自律性を尊重するということは、患者が十分な情報に基づいて自らの治療を選択する権利を支持し、その選択を尊重することを求められます。
- 医療従事者は、患者が自律的な意思決定を行えるように、必要な情報を提供し、患者の選択を支援する責任があります。
2. 善行(Beneficence)
- 善行とは、他者の利益を最大化し、害を最小化するように行動することを指します。
- 医療従事者は、患者の健康と福祉を促進し、最善の利益を提供するために行動することが求められます。
- これには、患者の健康状態を改善するための最良の治療を提供し、害を避けることが含まれます。
3. 無危害(Non-maleficence)
- 無危害は、「害を与えないこと」を意味します。この原則は、医療従事者が患者に対して意図的に害を与えないようにする責任を負うことを強調しています。
- 「害を与えない」という倫理的義務は、治療のリスクと利益を慎重に評価し、患者に対して不要な苦痛やリスクを避けることを求めます。
- この原則は、治療の選択において重要な考慮事項となります。
4. 正義(Justice)
- 正義は、公平で公正な扱いを保証することを意味します。
- 医療における正義の原則は、医療資源の配分が公平であること、すべての患者が平等に医療サービスを受けられることを保証することを求めます。
- また、患者の治療において偏見や差別がないようにすることも含まれます。
形式的正義の原則 (The Principle of Formal Justice):
- これはすべての正義理論に共通するものであり、伝統的にはアリストテレス (Aristotle) によって提唱されたとされています。
- この原則は、正義 (justice) とは「等しい者は等しく扱われ、不等な者は不平等に扱われるべきだが、その不平等は適切な不平等に比例したものでなければならない」という考え方に基づいています。具体例:
- 学校での成績に基づく奨学金制度では、成績が同等の学生には同じ額の奨学金が与えられるべきですが、成績が異なる場合は、その成績差に応じて奨学金の額が異なるのが公平だとされます。
功利主義的正義論 (Utilitarian Theories of Justice):
- この理論では、正義とは社会全体の幸福 (happiness) を最大化することだとされています。つまり、利益 (benefits) と負担 (burdens) の分配は、どれだけ多くの人々に善 (good) をもたらすかで判断されます。この理論の具体例としては、公共政策の決定において、多数の人々に利益をもたらす政策が正しいとされることが挙げられます。具体例:
- 医療費の予算配分において、限られた資源を使って最大限多くの人々が救われる施策が採用される場合です。例えば、重病患者一人に多額の治療費を投じるよりも、予防接種プログラムを実施して多くの人を病気から守る方が、全体の幸福を増やすことになると判断されることがあります。
平等主義的正義論 (Egalitarian Theories of Justice): ロールズ (Rawls)
- ロールズは「公正としての正義 (justice as fairness)」という考え方を提唱しました。彼の理論では、社会的なルールや資源の分配が公正であるためには、人々が「無知のヴェール (veil of ignorance)」の背後にいる状態でそれらを決定することが必要です。無知のヴェールとは、人々が自分の社会的地位や能力を知らない状態で意思決定を行うという仮定のことです。この状態であれば、自分が不当に不利益を被らないよう、誰にとっても公平なルールが選ばれるとされています。具体例:
- 例えば、税制の決定において、自分が富裕層か貧困層かが分からない状態で決定を行うと、多くの人が累進課税 (progressive taxation) を支持するでしょう。これにより、富裕層からは多くの税金を、貧困層からは少ない税金を徴収する公平なシステムが成立する可能性が高いです。
リバタリアン的正義論 (Libertarian Theories of Justice): ノージック (Nozick)
- ノージックは、個人の権利と自由を最大限に尊重する理論を提唱しています。彼の理論では、社会的な財の分配や所得の再分配を重視せず、むしろ公正な手続き (fair procedures) に基づく自由な取引や取得が重視されます。このため、国家の介入は最小限であり、人々が自分の財産や資源をどう使うかは個人の自由であるとされます。
ノージックの正義論 (Nozick’s Theory of Justice):
- ノージックの理論は3つの原則に基づいています。
- 取得の正義の原則 (principle of justice in acquisition):
- 自然資源や財産が誰の所有でもない場合、それを正当に取得する方法を示す原則です。たとえば、無主の土地を耕して農地に変える場合、それが公正に行われている限り、その土地を所有する権利があるとされます。
- 譲渡の正義の原則 (principle of justice in transfer):
- 財産が他者から譲渡 (transfer) された場合、取引が自発的で公正である限り、その譲渡は正当であると考えます。これにより、自由市場経済において人々が自由に財産を売買することが正当化されます。
- AさんがBさんから自発的にお金を支払って土地を購入した場合、これは公正な取引とみなされ、その土地の所有権はAさんに正当に移ります。
- 矯正の原則 (principle of rectification):
- 過去の不正な手段で取得された財産や権利については、適切に矯正されるべきだとする原則です。これは歴史的に不正な取引や強制的な奪取によって不当に得られた財産を、どのように修正すべきかに焦点を当てます。
- もしCさんが過去にDさんから不当に土地を奪った場合、矯正の原則に従い、Dさんにその土地を返還することが正義となります。また、不当な利益を得た場合、それに対する賠償 (compensation) も必要になるでしょう。
- 取得の正義の原則 (principle of justice in acquisition):
このように、3つの正義論はそれぞれ異なる基準で「公正さ」を定義し、具体的な状況に応じた判断が異なります。功利主義は全体的な幸福の最大化を目指し、平等主義は公平な分配を重視し、リバタリアニズムは個人の自由と権利を最も重要視しています。

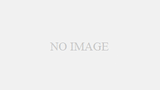
コメント